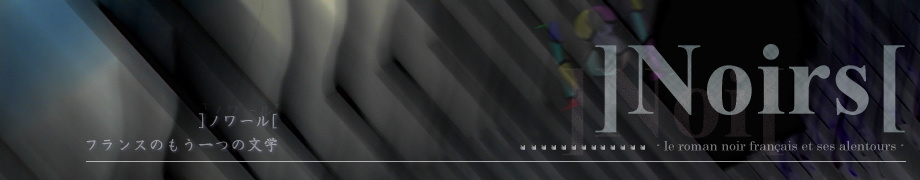 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
殺戮の記憶
〔ヤスミナ・カドゥラ/YB論〕
|
|
2003年9月
Tag: 論考。現代アルジェリア史、カドラ
|
|
|
|
|
|
|
毎朝報告書に目を通す。子供が殺された。家族が皆殺しにあった。列車が炎上した。村の大半が壊された・・・。夢でないか。血が出るほどつねってみる。悪い夢ではないようだ。アルジェリアの街中、同胞がありえない残虐さで殺し合っている。
|
|
|
『モリツリ(死すべき者へ)』(1997年)
|
|
|
ロブ警視を主人公にした「アルジェリア3部作」、そして以後の活動を通じてヤスミナ・カドゥラ(1955‐)は現代アルジェリア最高の作家という評価を得た。「仏語圏で最重要な」と付け加える者もいる。人々はカドゥラ著作の強度を前に蒼白となり、言葉を失った。ここには死の記憶、虐殺の記憶で埋め尽くされたアルジェリア90年代が広がっていた。
|
|
|
カドゥラ作品はアルジェリア現代史の混沌と重なりあっている。
|
|
|
94年は軍事政権、反政府政党の穏健派、テロリスト化した過激派の間で対立が深刻化した年だった。軍事クーデターで国防相ゼルアールが権力掌握。穏健派は95年に「ローマ議定書」を結び内戦鎮圧に向けた歩み寄りを見せる。政府側はこれを拒否。軍部を中心とした対ゲリラ壊滅戦が続けられる。街中では危険分子の拉致が恐怖を撒きちらす(94‐97年で数百件の報告あり)。過激派側からの報復テロは激しさを増し、ここでも一般市民が犠牲となる…まさに悪循環、カドゥラの仏デビュー作『モリツリ』〔註1〕はこの殺伐とした雰囲気を描き出していく。
|
〔1〕 本作の出版は97年であるが原型となった『巨人マゴグ』は94年に書かれている。
|
|
|
|
|
 |
|
|
『白を重ねて』の舞台の一つとなった
カスバー(Le Casbah)地区
|
|
|
|
|
|
死の風景は都市の日常に組みこまれている。爆破テロ、「耳から耳へと大きく喉を切り裂く」。アラブ系のテロリストが得意とする暗殺方法は「アルジェリア3部作」でも頻繁に現れる。『モリツリ』第五章、警官たちのミーティング中に署を狙った無差別爆破テロが起こっている。
|
|
|
大通り。通行人は何が起こっているのか分からないままこのドラマを見つめている。仰向けの車が炎上してる。黒い煙が建物の正面に縞模様を描いている。バラバラになった死体が舗道で血を流していた。
|
|
|
失踪女性の調査と知識人を狙った暗殺事件の解明、『モリツリ』は二重の筋を軸にして進んでいく。冒頭パーティ場面で主要人物たちが揃い踏みし、物語は起伏の多いジグザグした展開をみせていく。複雑な人間関係を整理するのに一苦労だが…アルジェリア内部の権力地図が鮮やかに浮かびあがってくる。
|
|
|
カドゥラは災禍の元凶を「財政界のマフィアたち」と規定する。キャバレー「赤い冥府」周辺に巣食う魑魅魍魎たち。同じ連中が都市部テロリストを操っている様子も見えてくる。イスラム原理主義の過激派は西欧化された知識人を攻撃目標としているが、それさえも「操られて」いる。誰が誰を操ってるのか?捜査は難航し、ロブ警視の同僚セルジュが犠牲となる(「今、彼の首と胴体をつないでるところだ…」)。最後にロブは敵の処刑へと向かう。
|
|
|
虚構から一度離れてみる。アルジェリア政府は内部状況が表沙汰になることを嫌っている。極端なまでの情報統制、検閲システムは有名だった。地中海の対岸に位置するフランスでさえ正確な状況を把握するのは難しかった。生々しい現代アルジェリア像は衝撃となった。『モリツリ』はこの年の813長編賞を獲得する。カドゥラは評価に応えるように『白を重ねて』(97年)、『怪物の秋』(98年)でロブ警視の地獄巡りを推しすすめていく。
|
|
|
|
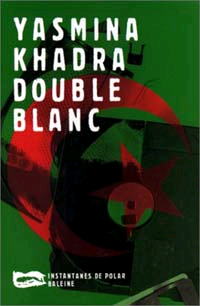 |
白を重ねて |
| ヤスミナ・カドゥラ著 |
|
〔初版〕 1997年
バレンヌ社(パリ)
叢書アンスタンタネ 81番 |
|
Double blanc / Yasmina Khadra
-Paris : Editions de la Baleine.
-(Instantanés de Polar; 81). -1997. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
『白を重ねて』の各国語翻訳版
左から順に英・独・西・伊です。
|
|
|
|
|
|
『白を重ねて』はカドゥラ流犯罪小説の完成形となっている。冒頭で提示されるダイイング・メッセージ《HIV》が作品の速い展開を促していく。お馴染みのロブ警視、リノ警部といったメンバーに巨人エヴィグが参入。力を持てあました寡黙な巨人の合流は捜査過程にユーモアとアクションを付け加える。《謎解き》という犯罪小説らしいエンターテイメントの側面が補強されている。
|
|
|
「幾つか質問が」
「何の話かね」
「お喋りするには室内が良いかと」
「残念ながら鍵を失くしてね」
エヴィグに「鍵を失くされたそうだ」と言ってやった。
うなずいて石段を上っていくエヴィグ。豪邸の扉を蹴り破った。
|
|
|
都市を背景としたリアルポリティーク、こちらは前作を踏襲している。告発文書を準備していた外交官ベン・ウダが暗殺される。テロリスト4人の肖像画を描き出されていく。『モリツリ』の風景は性産業近辺だった。『白を重ねて』ではテロルの生態系が表立ってくる。テロリストたちは口封じのために抹殺され、警官たちの包囲を前に自決、舞台から次々と姿を消していく。「駒」に過ぎない。華やかなテロリズムは騙し絵であり、最後に表面化してくるのはやはり資産家たちによる私怨の清算である。
|
|
|
『モリツリ』から『白を重ねて』。カドゥラは純粋な犯罪小説を志向しつつ現代アルジェリアの問題を結晶させた。初期の2作はこの点で優れている。もちろん主人公ブラヒム・ロブ警視の造形も忘れてはならない。ユーモアに富み、私生活では良き夫、良き父親。そして良きイスラム教徒。若干マッチョなのが難点かもしれない。否応のない現実に目が覚めてしまった理想主義者。あるいは諦めの悪いペシミスト。「夢破れて」という主題はカドゥラ全般に見られるものでロブ警視も例外ではない。現代アルジェリアを憂える表現は特に『モリツリ』で顕著で、それが比喩となって不意打ちしてくる時の魅力は格別である。
|
|
|
カドゥラは作中で「敵」にも発言の機会を与えている。テロリストの首謀者曰く : 「アルジェリアらしいアルジェリアを夢に見ていた。イスラム学校やモスクがあって…」。無数の夢が現実に押し潰され、狂暴な形をとって回帰してくる光景。カドゥラ著作は複雑な風景を抱えている。犯罪小説に閉じこめてしまうのは不可能だった。3部作の最終作『怪物の秋』(98年)で既にジャンル離脱の兆候を見て取れる。
|
|
|
私的な犯罪から集団的テロルへの移行。それは現実のアルジェリア社会情勢とも密接に関係している。97-98年はアルジェリアの極限状況だった。かつての反対勢力(イスラム救国戦線FISと軍事部門イスラム救国軍AIS)は元リーダーの釈放(97年7月)をきっかけに穏健化。逆に孤立化した過激派が地方部での虐殺を重ねていく。毎月のように報告される数百人規模の殺戮、死者の総数は10万とも20万とも言われている。正気の沙汰ではない。
|
|
|
この状況を前にカドゥラ作品は変質していく。虚構と現実のバランス感覚が微妙に変化して重点が後者に置かれていく。それはテロ集団をどう呼ぶかという細部にも現れてくる。『モリツリ』と『白を重ねて』では「奴ら」という婉曲な表現が用いられていた。『怪物の秋』では公然と「GIA(武装イスラムグループ)」と名指しされるようになる。カドゥラなりの宣戦布告と捉えてもいい。
|
|
|
『怪物の秋』では謎解きの要素が完璧に消えている。前2作をあれほど豊かにしていた都市の犯罪絵巻もない。冒頭でロブ警視は休暇を言い渡される。上層部の機嫌を損ねたという噂はすぐに広まっていく。彼の言動をかねてより快く思っていなかった者たちが暗躍しはじめる。公然とした非難(「お前は終わったよ」)、家宅侵入者の痕跡(「そいつは電気を消すのを忘れていったようだ」)、露骨なプレッシャー(「だから不可能を要求してるわけじゃない」)。状況だけが悪化していく。第2部の終わり、喫茶室にいたロブ、リノ、エヴィグの3人が爆破テロに巻きこまれる場面でひとつの頂点に達する。
|
|
|
入口近くの連中は瓦礫に埋もれていた。壊れた人間の一人はギャルソンだった。青年は片腕を動かそうとする。無理だと気づいて「信じられない」と蒼白な顔に。霧の中を歩き回っている女性が一人。顔が爆風で千切れ両手を突き出している。ホラー映画から抜け出してきた姿だった。
「私の鞄は?」
血まみれの少女が叫んでいた。埃まみれで絶望的に探しまわっている。目の前の歪んだ顔の男、ふくらはぎの下敷きになった血塗れの足にも気づかない。
「爆弾だ!爆弾だ!」
気が触れたように誰かが叫んでいた。
|
|
|
物語はこれでは終わらない。旧友の葬儀のため帰省したロブ警視は山間部のゲリラ襲撃に遭遇する。村人も自衛のため武装し、組織化された抗戦を試みるが…物量を誇る敵の前になすすべはない。「女と子供の悲鳴」が銃声と合唱する中で家々は燃え上がっていく。
|
|
|
ロブは休暇終了後に辞表を提出する。退官パーティーでは人々から(かつての敵からさえ)ねぎらいの言葉が与えられる。ロブは「休息」を求め、「人生のもっと単純な事と折り合いをつけよう」と願う…残念なことにカドゥラ著作にそんな安らぎは存在していない。「いつも善人が死んでいく。神が傍にいてほしいと願うから。悪人が死を願うから」
|
|
|
事件-捜査-解明という物語さえ不可能になってしまった国の犯罪小説。『怪物の秋』をそう呼ぶこともできる。聖戦という名の虐殺が繰り返されている場所で通常の推理小説的な手続きがどれほど意味を持っているのか確かに疑わしい。「アルジェリア3部作」ではひとつの世界像が生成し成熟していく実感があった。『怪物の秋』で「警官」という設定は限界にきていた。
|
|
|
99年、愛好家に一冊の贈り物が届けられた。90年にアルジェリアのみで出版されていたカドゥラ名義の処女作『メスを手にした殺人者』の再刊である。ロブ警視が初登場した一作、全体としては当時よく見られたサイコキラー物の一変種になっている。緊迫感を欠いていて「凡庸」〔註2〕という批判も避けがたい。しかし後の3部作では触れられないロブ警視の個人情報(家族構成など)が含まれていたし、また、後に高度な展開を見せる幾つかの要素(殺人鬼の神経症的口調。誇大‐被害妄想。死を劇的に演出しようとする姿勢)を見てとれる。カドゥラ原型を見せてくれる貴重な再刊ではあった。
|
〔2〕 タン・ノワール誌第3号(2000年)、クロード・メスプレッドによる時評より。
|
|
ノワール作家としてのカドゥラはこの時点で終結する。以後拠点を大手ジュリアール社に移し純文学の枠で作品を発表していく。「格上げ」なのだが、実はノワール系作家の純文学化は危険をはらんでいる。死/暴力といった主題から解放され、推理小説の枠組みを放棄したときに作品の緊張感が失われる。ダニエル・ぺナック、トニノ・ベナキスタが評価を落としていった。カドゥラも不安がないわけではなかった。しかし『神の小羊』(98年)、そして『狼は何を夢見るのか』(99年)がこの作家は例外なのだと証明することになる。
|
|
|
『神の小羊』と『狼は何を夢見るのか』は補いあう形になっている。前者は三人称、農村部を主人公として内戦をシュミレートしていく。後者では一青年がテロリスト化していくまでのプロセスが綿密に、こちらは一人称で描き出されている。
|
|
|
『神の小羊』の評価は高い。本作を(現時点までの)カドゥラ最高作とする者も多い。今までにない緩やかな導入部、求婚のエピソードが軸となって失望、嫉妬や葛藤が生み出されてくる。青年たちの将来は悪い方に動いていく。他人事だった「戦争」がゆっくりと村に入りこんでくる。求婚に敗れたカダはFISの兵士としてアフガンに従軍、彼の帰還が物語の折り返しを告げる。「橋に置かれたナップザック」、「導師ハジの頭部」。殺人劇の開始である。後半部は悲劇的な加速度を増し、最初主人公に見えた4人(アラル、カダ、ジャフェル、サラ)でさえ生き延びることは出来ない。最後に残るのは?ちょっとした驚きが読者を待っている。
|
|
|
一方の『狼は何を夢見るのか』はカドゥラ著作で最も激しい暴力描写が特徴である。一青年の挫折をモデルとしてテロリスム内部のデリケートな力学・心理学が緻密に解析されていく。例えば都市部テロリストからあぶれた者が山間部に流れ武装集団に回収されること、望んでゲリラ化しているわけではなく、捨て駒だという冷めた実感もあること…絶望的な風景が見えてくる。
|
|
|
農村/都市、集団/個人、三人称/一人称。対照的な世界構築である。とはいえ10年(1988-98)という期間で日常が加速度的に悪化、取り返しのつかない解体に辿りつく同一の歴史感覚は共有されている。この2作が噛みあったときアルジェリア90年代をめぐる一貫した、最も切実な風景が立ち現れてくる。
|
|
|
ヤスミナ・カドゥラというペンネーム(「ヤスミナ」は女性名)に隠れていた作家が姿を現したのは99年だった。彼=モハンメド・ムレスールが現役軍人であること、80年代にも本名で作品を出版していたこと、ニーチェ、マルクス、ドストエフスキー等を愛読していること、情報が一つ一つ公開されていった。
|
|
|
00年から02年までは作家にとってアイデンティティ模索の時期となる。匿名で、しかも犯罪小説という周辺領域で書き続けてきただけに「作家として認めてほしい」という欲求は強いものだった。軍隊を退役して家族とともにメキシコへと移住、自伝的色彩の強い小説を2作仕上げている。
|
|
|
まずは幼少期を振り返った『作家』(00年)、さらに02年には仏滞在を元にした『言葉の簒奪』。どちらの作品も質の高い文体で貫かれている。特に後者は幻想、妄想を巧みに扱っていて(主人公の小説家はロブ警視や小人ザンといった旧作の登場人物と対話を交わす)読み応えのある作品だが…次段階を睨んだ間奏の印象も強い。
|
|
|
作家カドゥラの「沈静化」はアルジェリア状況とも平行している。98年に大統領ゼルアールが辞任、翌年の大統領選でブーティフリカが当選。この政権交代を境に事態は急速に収束、再建、「民主化」へと向かっていく。少なくとも「虐殺」の文字と写真はメディア上から消えた。アルジェリアが殺戮から抜け出した後でカドゥラ著作がどうなっていくのか微妙なところである。
|
|
|
カドゥラ著作に一貫している特徴。1)展開の速さ。2)対話の妙とユーモア。3)抑制され、効果的に描かれていく現代的暴力。4)人間関係や場を把握していく能力。5)比喩の形で現れる詩性。6)現実に裏打ちされた骨太な理想主義。
|
|
|
アルジェリア犯罪文学・カドゥラ編の締め括りに寓話をひとつ。勢いで書き流した感もあるがカドゥラの手にかかると90年代型テロリスムでさえ隠喩に変わってしまう:
|
|
|
「シド・アリは虫を指でさした。「カマキリは元々葉っぱだった、知ってるか?」、そう聞いてきた。いや、俺はそう答えた。アリはカマキリと葉の話をはじめた:
反抗的、傲慢な木の葉だった。秋が来て枝から切り落とされるなんて真っ平だった。自分は凄いのだ。他の枯葉と一緒に朽ちてしまう、風で追われて泥まみれになっていく。何て恥ずかしい。「信じるのは自分だけ」、そう誓ったのだった。
次の季節まで生き延びたかった。熱意と闘争心に負けた自然は木葉を虫に変えてやった。さてどうなるだろうか、と。カマキリはこうして生まれてきた。荒々しく、言葉少なで野心的な動物だった。奇跡に舞い上がる。枝を攻撃して踏みにじる。他の虫を食べはじめる。偉そうに振舞うカマキリを止める者はいなかった。目が眩んでしまったのだ。何を証明したいのか知らないがすれ違う者全てを貪り喰らう。自分を愛してくれた者も含めて」
鳥が飛んでいく。
「綺麗な寓話じゃないか」、ナファは認めた。
「あぁ。詩人の言葉に耳を傾けておくべきだったな」
|
|
|
|
|
|
カドゥラは紛れもなく一級の作家である。しかし90年代アルジェリアを描き出したのは彼一人ではない。カドゥラ型方法論への優れたアンチテーゼとして異形作家Y.B.(ヤシール・ベンミルド)を挙げておこう。
|
|
|
両極端な作家である。ニーチェ、ドストエフスキー、マルクスといった参照から分かるようにカドゥラは西欧近代を背景にしている。19世紀文学から神経症的な文体を譲り受け、徹底的に削ぎ落とされた(あの焼けるような)文章へと再生していく。アルジェリアの混沌を前に「描写」しようという姿勢にもつながっていく。あくまでも古典的なアプローチである。
|
|
|
Y.B.は同一の状況を分裂症的に作品化してしまう。現代アルジェリアの分裂を作品によって「反復し」、それを「内側から生きて」しまう。その結果生み出された『零に死す』(01年)は政治的笑劇となる。
|
|
|
|
 |
零に死す |
| Y.B.著 |
|
〔初版〕 2001年
ラテ社(パリ) |
|
Zéro Mort / YB
-Paris : Editions Jean-Claude Lattès. -2001. |
|
|
|
|
|
最後は殺せ-殺せ-殺せ。
90年代を通して奴らがやったのはまさにそれ。凄い才能。ジャーナリスト22人、政治家19人、司法官16人、組合活動家14人、サッカー選手11人、審判9人、アルビノ7人、ベルベル人軍人5人、スペイン修道女2人、シェパード1匹。
続くのは「2000年までに20万人殺そう」大作戦。軍部とGIAの協力もあって大成功。アルジェリアは民族殺戮市場で世界トップに躍り出る。
|
|
|
雰囲気は伝わるだろうか。Y.B.は軽さを演じ、シリアスな状況を確信犯的に踏み抜いていく。西欧近代が練りあげていったリアリズムは最初から念頭にない。フリーフォームかつフリースタイル、気分に応じて場面を即興、確かに「小説」なのだけれどここにはルポルタージュ形式(「こちらY.B.」)、散文詩から韻文劇まで放りこまれている。翻訳不能なフリークトーンも多数収録。この取りとめのなさは筋立てのレベルでも同様。
|
|
|
作品を彩るのは極薄のキャラクターたち。テロリスト集団「イスラム剣士」(総勢6名)、政治家兼軍人、政治評論家Y.B.、そして「死の天使」等々。冒頭三ページ目、司教暗殺を企てた青年ユーセフが射殺される。殉教者になる予定だったが…第2章ですぐ「復活」。スーツケースを抱えた「死の天使」が現れてインタビューを開始する。
|
|
|
「さて。もし僕が間違ってたら“ストップ”と言ってくれ。
1)君は神の名において殺し始めた。
2)神という名の殺人者の名で人を殺した。
3)殺人者の名において殺した。
4)殺人が君の新たな神となった。正しい?」
「あ?」
「正しいようだね」
|
|
|
万事快調。後半部ではX‐ファイルのスカリー捜査官が登場。コーラン詩篇に秘められた暗号を解読しながらアルジェリア事件の核心へ迫っていく…この辺りのB級感覚はOKなはずである。
|
|
|
現代と戯れる姿勢は細部にも見てとれる。青年ユーセフの財産は「コーランのCD‐ROMとプレイステーション」。世紀末に現れた由緒正しい悪魔「マリリン・マンソン」の言及も忘れない。マスカルチャー由来の固有名は目配せのようなものだ。こういった記号を通じてカドゥラ著作にはない「もうひとつのアルジェリア」が見えてくる。
|
|
|
Y.B.とカドゥラが顔をあわせたら。興味深い顔合わせである。言葉を通じたやりとりは以前からあった。98年、Y.B.は「アルジェリア:ヌーヴォーロマン」という論考を発表、カドゥラを冒頭で取り上げる〔註3〕。『神の小羊』発表直後のカドゥラは「現代アルジェリアの大作家」扱いである。逆にカドゥラは「恐るべき才能」とY.B.を形容する(『言葉の簒奪』)。世代と方法論の違いを超えてリスペクト成立、アルジェリア文学の2トップ体制が成立するかと思われたが…。『言葉の簒奪』では二人がTV出演したときの様子が語られている。どうやら話は噛みあわずに終わったようである。
|
〔3〕 ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール誌、1764号、1998年。
|
|
|
|
|
 |
|
|
ヤスミナ・カドゥラ(左)、Y.B.(右)
|
|
|
|
|
|
このニアミスには納得がいく。Y.B.の辿ってきた道筋をまとめておこう。彼を有名にしたのはアルジェリア日刊紙に連載していた辛口政治時評「神が言うには」である。ユーモアを交えながらも政府/軍部を名指しで批判。これで一挙にブラックリストの仲間入りを果たす。
|
|
|
97年11月に「Y.B.失踪」のニュースが流れる。情報局による拉致・監禁事件。言論弾圧、フランスでも問題となった。翌日無事に姿を見せたがすぐにパリへ脱出している。98年に『神が言うには』を出版(ラシド・ミムニ賞)、翌年には件の失踪事件に言及した『釈明』を発表している。ロマネスクな展開を見せた『零に死す』は3作目となる。
|
|
|
Y.B.による現状把握はカドゥラと全く異なっている。『モリツリ』は災禍の元凶を「財政界のマフィア」と表現していた。『釈明』はむしろ「軍‐政府による寡頭政治」を強調している。どちらも虚構、解釈とはいえ実情はY.B.の描いたアルジェリアに近い。軍上層部の続けている権力闘争は公然の秘密である。ある日刊紙は「アルジェリア7人衆:キーパーソン」を紹介していた〔註4〕がいずれもが軍関係者である。このうちの一人メディエンヌ幕僚長(超大物)は『零に死す』にゲスト出演、テログループと接触を取る。
|
〔4〕 ル・パリジャン紙、2001年6月19日付けの記事より。
|
|
メディエンヌ幕僚長:
君たちがぁぁぁ。喉を切りぃぃぃ、略奪するのを許しましたぁぁぁ。友よぉぉ、お金は貯まってるかいぃぃぃぃ?
導師メディ:
問題がぁぁ違うよぉぉぉっぉぉ。十年でぇぇぇ友達たくさん失くしたよぉぉぉっぉぉ。
|
|
|
Y.B.は政治風景を力技で解体していく。冗談であって冗談ではない。『釈明』に収められた幾つかの機密文書も同様で、実質的にはユーモア/幻想でコーティングされた内部告発(内部告発風の三文小説?)である。敵は軍閥。カドゥラが将校であった事実を思いかえしてみると…作家Y.B.がカドゥラのアンチテーゼになっている所以である。
|
|
|
Y.B.は「アルジェリア3部作」を「毒々しい詩的神話に満ちた推理小説」と形容した。なぜ「神話」なのか見えてくる。筆者自身を含め、当時多くの人々が『モリツリ』に、『神の小羊』に現代アルジェリアの姿を読み取っていた。ところがY.B.にとっては‐彼自身の“リアル・アルジェリア”からは掛け離れた‐高度な虚構だった。「カドゥラ著作とはアルジェリアの現代神話である」、偶像破壊的な魅力をたたえた発言はY.B.らしいものだと言えよう。
|
|
|
|
|
|
虐殺の風景があった。
|
|
|
記録ではなく記憶へ。強迫観念へ。怒りに満ちた憂愁でねじ伏せる、デュオニソスの哄笑で破壊する。両者とも現代アルジェリアから生まれてきた感性と知性である。死んだ者が蘇るわけではない。最初から分かっている。殺戮の記憶を持った小説がある。それだけで既に何かではないのか。犯罪小説出身のアイスキュロス、反骨精神に貫かれたアリストファネス。死のアルジェリアは語り部としてカドゥラとY.B.を選び出す。判断は誤ってはなかったはずである。
|
|
|
|
|
|
                   |
|
|
] Noirs [ - フランスのもう一つの文学 by Luj, 2008 - 2010
|
|