|
| 肩にはリュック、片手にギター。故郷スイスから遠くへ離れ、マリーヌは海へと向かった。 |
| ヒッチハイクで車を乗り継いでいく。ためらいは残っている。もし南仏でも同じだったら。逃げ出そうとしてた同じ現実が待っていたら。孤独感、悲しさ、怖れ、吐き気が止まらない。南仏は違うはず。太陽がある。新しい光、新しい生活…女はボルドーの小さな村へ流れ着いた。村の名士に囲われる形で村に住み着くが、やがて姿を消す。 |
| ホームでは姪が手を振っていた。アントワ−ヌは47年の人生でパリを離れた経験がなかった。雑誌懸賞でボルドー旅行を当てた時も素直には喜べなかった。ボルドーで村人に案内してもらう。「海のような葡萄畑でしょう」、葡萄の木が黒く並んでいる。頭上をカラスが飛んでいる。寒気がした。 |
| 映画、クロスワード、推理小説…昼間の退屈な時間を潰していく。深夜に女の悲鳴が聞こえた。「子供では」。違う。そうじゃない、叫んでいるのは大人の女だった。村人に聞いても曖昧な答え、首を振るだけだった。初めてワイン貯蔵庫に案内してもらった時にフレスコ画を見つけた。「マリーヌとジャン」、作者の署名があった… |
| 冒頭に登場したマリーヌが生きているのか、死んでいるか、謎のちらつかせながら読み手を異界へと案内していく。アモツはこの後SFや怪奇幻想の短編も残していくのだけれど、『酒蔵』の段階でもその傾向は既に現れていて、見えるものと見えないものの戯れを器用に操っている。 |
| 後にリヴァージュ社に移っていく才女クロード・アモツの処女長編。比較的実験的な作風が多かった叢書オール・ノワールで、この瑞々しいサスペンスは一作だけ異なった輝きを帯びていた。 |
|
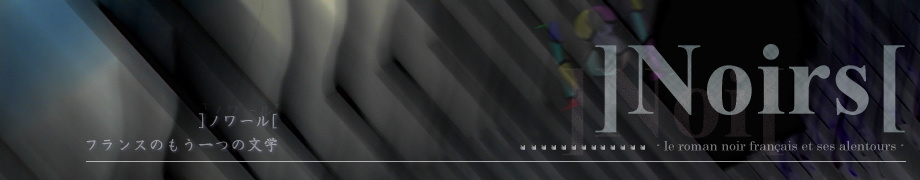


![]() 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 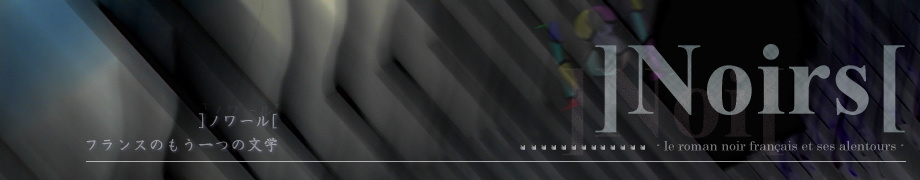


![]() 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
海外格安航空券 海外旅行保険が無料!