|
|
顔を噛んでくる風が冷たかった訳ではない。断崖で裂けていく荒波の冷たさでもない。この寒気は遺体を納めた棺の蓋がギシギシと鳴っているせいだった。町長カルソフの妻。誰かが頚部を切断、葬儀は頭部を欠いたままで執り行われていた。 |
町長の脇には二人の姉弟が並んでいる。父親にとってはどちらも出来損ないだった。上の娘リヴィアは反抗的な言動を繰り返している。後継ぎと見こんだ息子オレールは音楽にうつつを抜かしている。家にあったピアノは廃棄していた。指を潰し、夢を潰してやったのだが同時に息子は言葉を失ってしまう。毎日のように美術館に入り浸り、レンブラント作の『アブラハムの犠牲』を眺めている失語症青年を町民は奇異な目で見つめていた。 |
カルソフ夫人の葬儀には二人の警官も参列していた。「あの風車は何?」、目を上げたフランク・アルベルティニが尋ねた。「二十年以上前にアイルランド人一家が買い取ったとか云う代物ですよ。建立は15世紀にまで遡るとか」 |
聞きこみを兼ねて風車を訪れる。アイルランド一家の末裔だという女サマンサが住んでいた。自称「雲の狩人」。室内には町のはみ出し者たちが集まっていた。アルベルティニはサマンサの信頼を得て事件調査の協力依頼に成功する。ようやく事件解明への一歩を踏み出したと信じたアルベルティニ。だが彼の元に第2の凶行の報せが届く。今度は足首から下を切断された遺棄死体だった… |
E‐ディット社で公刊されていた「ジャンヌ・ドゥボール女警視」シリーズは04年に完結しているのですが、その続編(というか新展開)として発表されたのが本作。今度はジャンヌが失踪し、同僚アルベルティニによる「ジャンヌ探し」がサイドストーリーに組みこまれた形となっています。 |
|
英語圏の猟奇スリラー、独白を多く含んだ心理小説、人物と世界の歪みを強調するノワール指向。成分分析をしてみるとこの3つが主になります。物語に強弱のアクセントが足りないのが難点で、スリラーを期待して読んでしまうと当てが外れるかも(盛り上がりが皆無なのです)。一方この起伏のなさ、零度の物語がうねうね進んでいく感触が持ち味として確立されている感もあります。もう一皮剥けるとミシェル・ルブラン賞や血のインク賞辺りを獲るのではないのかな、と。
|
|
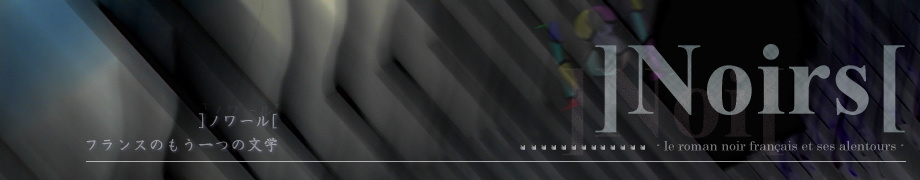


![]() 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 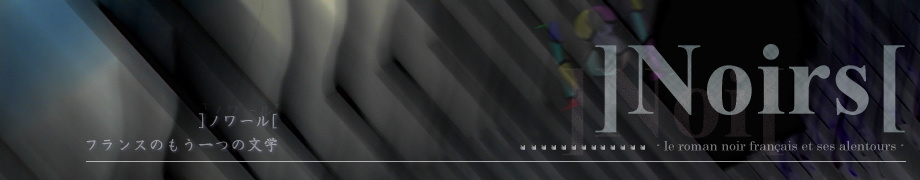


![]() 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
海外格安航空券 海外旅行保険が無料!