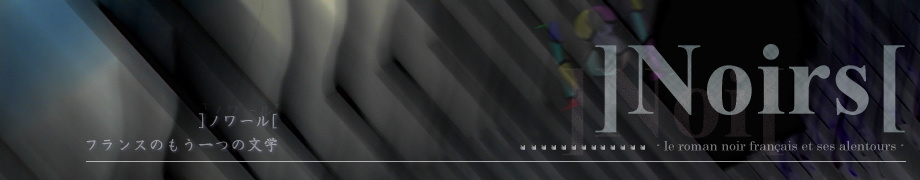 |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
| 【1】 - 【2】 -【3】 - 【4】 | ||||
|
|
||||
|
鳥女はポーランの死体に冷ややかな一瞥を与えた。素晴らしい威厳だった。アドレナリン値が急上昇、彼女の虜になっているのが良く分かる。同じく彼女に惚れていたゴム男はといえば、不意を打たれた様子だった |
||||
|
「ペペットちゃん。俺約束し…」 |
||||
|
男が言葉を言い切る暇を与えなかった。羽で平手打ちをピシッと一発。 |
||||
|
「ペペットって呼ばないでよ。君をまたリクラ君って読んであげようか」 |
||||
|
ゴム男ツアーのポスターに「リクラ」というあだ名を入れようか、そう提案したのはポーランだった。当の本人は「ブルガリア風の名前なんて古かりや」と嫌な顔をしていた。「ノビ・スギタ」や「ヤワラカ・シアーゲー」、自分であれこれと変名を出してくる。座長の判断は「この手の貧相な言葉遊びは出し物のイメージを損なう」だった。結局は「ゴム男」で続ける羽目に。鳥女用に用意された芸名も却下された。「子」で終わる名前は舞台ではよくあるのだがどうも安っぽい。だから「鳥女」でいくことに。本名は未詳。秘密があるのも魅力だった。 |
||||
|
鳥女がこっちを見つめていた。情けない姿をしていたに違いない。女は王冠を拾い上げて放り投げてきた。 |
||||
|
「ちゃんと服着てよね」の命令。「クーデターの直後みたいよ」 |
||||
|
王冠を頭に載せる。端の壊れた王杖を拾い上げる。ゴム男は今にも倒れそうな様子だった。手にした銃で僕たちを脅すことも忘れている。僕は男の指からそっと拳銃を引き抜いた。 |
||||
|
鳥女は行ったり来たりを繰り返す。時々立ち止まって爪で床板をキーキーと引っかいている。彼女の癖だった。 |
||||
|
「私もうペペットじゃないもん。ウズラちゃんでもないもん。ニワトリちゃんでも…おぉ。お金に目がくらんで人を殺めるなんて。君は身を滅ぼすの。己の羽で飛び立とうとして〜」 |
||||
|
ゴム男のククッという笑い声。女は一瞬足を止めてゴム男をにらみ殺す。見事なワシ鼻は相手を突き刺さんばかりだった。 |
||||
|
「王様君」、鳥女の懇願。「こんな奴殺しちゃって。それから逃げましょう、一緒に」 |
||||
|
この気の強さが魅力だった。以前大きな事故に遭い、他の女性なら精神的に参ってしまうところを立ち直ったのもこの性格のおかげだった。元々は芸人の娘で、世界でも最も名の知られた奇術師と結婚、スパンコールに飾られた派手な生活を送っていた。ある日ラスヴェガスの「セザール・ハウス」、舞台で夫が脳卒中で倒れてしまう。不幸にも十八番を披露している最中だった。箱に閉じこめた妻を剣で突き刺し、その後さらに巨大な檻に閉じこめた雷鳥と体をチェンジさせるのである。呪文を唱えている途中で喉が詰まる、血が止まってしまう。奇術師としては見事な死ではあったが…妻にとっては悲劇だった。頭にトサカ、腕の内側に長い羽が残ったままだった。鳴き声に肢の動き…奇癖も現れてきた。魔術師が死んでしまい謎は永遠に解けないまま、女が元の姿(僕たちは気を使って「初期形態」と呼んでいた)に戻るのは不可能だと分かった時点で雷鳥は殺されていた。 |
||||
|
鳥女はポーランが雇った最初のアーチストだった。SF映画専門の衣装屋で女をみつけたのだが、実演などしながら細々と暮らしていたらしい。僕はといえば一目惚れ。何を頼まれても断れないくらいに。 |
||||
|
だからためらうことなく銃をゴム男に向ける。頭部への一発で射殺。ケープが汚れるのも気にならなかった。服が汚れるのは引金を引いた瞬間に分かっていた。でもお金が戻ってくるのなら衣装タンスごと新しく手に入れればいい。こだわりすぎてもしょうがない、時には捨て札も必要だった。 |
||||
|
|
||||
|
僕: 最初会った時ね、ポーランのことをモルモン教徒か何かだと思ったの。背が高くて、埃まみれになったビロードのベスト、タック入りのズボンにメキシカン・ブーツ、紐ネクタイに楕円形の鏡眼鏡、おまけに帽子をかぶっている。モルモン教徒に間違われてもしょうがないよね。昔警察で使われていたような古いシトロエンのワゴン車を税関の前に停める。クラクションを立て続けに鳴らして一帯の寝たきり連中を追い払っていく。車の脇に「ポーラン妙薬でハゲとお別れ」って書いてあった。 |
||||
|
僕は井戸の周囲のタイヤを塗りなおしている最中だった。8月の王国建国祭の準備だった。花束も増やしてみたけれど印象はいまいちだった。 |
||||
|
有刺鉄線の向こうから「王様!…王様!」の声。 |
||||
|
僕は黙殺した。男はワゴン車まで戻るとメガホンを手に戻ってくる。 |
||||
|
「王様!王様が必要としておられる座長でございます!」、怒鳴り声にびっくりした群集が数歩後ずさり。「何よあれ」、「何々」のささやき声。 |
||||
|
動けなくなった数人が窒息していた。 |
||||
|
僕は手で荘厳な動きを一つ、人々を黙らせる。正直「参ったな」の気もしていた。でも僕のキャリアを加速してくれる奴が現れたのだと分かっていた。 |
||||
|
人を惹きつける魅力の持ち主だった。業界にも通じている。人当たりの良い性格だったけど、毎日大量にミントキャンディーを食べる奇妙な癖を持っていた。太鼓腹、相手が誰だろうとキャンディを大盤振る舞いだった。僕なんて消化不良でゲップばかり。ゲップもミントでフレッシュだったけど。いい加減止めないと、そう思って飴を断り始めた。 |
||||
|
ポーランは座長としてヨーロッパ中の舞台を回り、米国ツアーで大成功を収めたそうである。いつも「ブック」を手放さなかった(仕事に絡んだ写真を貼り付けたノートのこと。業界用語って難しいね)。ボールペンで署名を入れた証言も残されていた。「妙薬で髪が生えてきました」(ブザンソン市のB氏)。「ポーラン博士のイヤリングで競馬三連が当たりました」(ヴズール市Mさん)。他にも何千と言う声が。間違いない、この男は只者ではなかった。 |
||||
|
「本(ブック)、人間が動物と違うのはこれだね」、男が近づいてくる。 |
||||
|
意味不明な発言もあったけれどそれは言わなかった。自分が未来のセレブに向けた転換期を迎えている。分かってはいたので大人しくしておくことに決めた。無能ではないと見せ付ける必要があった。ショービジネス、メディア世界の流儀を相手にしているのだから。細かな部分が気になったので聞いてみる。イヤリングで幾ら稼いだのかを聞いてみた。 |
||||
|
胸を反らして「凄いですよ」。 |
||||
|
この話題になると声が小さくなった。窓とリビングテーブルの間を行ったり来たり。 |
||||
|
「本当に凄いですよ…これで仕事用の車を手に入れました」 |
||||
|
ワゴン車の値段が幾らか考えてみる。男がミントキャンディーを差し出してきた。 |
||||
|
「あなたをスターにしてあげます」、言葉を続けていく。「スター誕生。人間が動物と違うのはこれだね」 |
||||
|
僕はうなずいた。 |
||||
|
「あぁ、話が早い。交渉成立」、キャンディーを差し出しながら微笑をひとつ。「理解しあえると思っていましたよ」 |
||||
|
ブックの写真、一番名前が知られていると言う二人の「創造物」を見せてもらった。この言い方がお気に入りらしかった。立ったまま靴をふくらはぎにこすり付けて艶を出している。さすが歴戦のプロだった。 |
||||
|
最初の写真。ガソリンスタンドのカフェテリア、合成樹脂で仕上げたテーブルの上で丸くなっている曖昧な物体。 |
||||
|
「これがゴム男。新入りの一人ですな。ルート66でツアー中のリハーサル写真です。ルート66をご存知?」 |
||||
|
「いや」、ミントのゲップをしながら僕。 |
||||
|
胃が燃えるんじゃないかと思った。写真を丁寧に見直していく。確かに、ケチャップの瓶の脇に顔らしきものが写っている。その隣、普通は手が置かれるべき場所、皿の上に足があった。フライドポテトが床に散らばっていた。 |
||||
|
「ルート66は」、飴を喉に放りこんだ男。「アメリカ合衆国を横切ってます」 |
||||
|
不意に男は口を閉じた。 |
||||
|
僕は写真を見つめていた。後ろの方、駆け寄ってくる看護夫の姿が写っていた。 |
||||
|
ポーランがこちらに身を傾けてくる。顔にフレッシュな息が吹きかかってくる。 |
||||
|
「決心ひとつですよ。明日、あなたもアメリカでスターに」 |
||||
|
心が乱れるのを必死に隠そうとした。 |
||||
|
アメリカで有名に… |
||||
|
「これ誰?」、僕は二枚目の写真を指さした。 |
||||
|
「鳥女をご存じない…」、小馬鹿にした口調だった。「情報通になっておきましょう。人間が動物と違うのはそれですよ」 |
||||
|
女はセパレートの小さな水着姿。素晴らしい。漆黒の羽に輝いているトサカ、長い両足に黒のストッキング(蹄は無いようだった)。「美・豪・富」誌のヴェラよりずっと綺麗だった。 |
||||
|
ポーランが僕の手からノートを奪い去る。 |
||||
|
「王様、栄光はあなたのものです。この世界の人々がかつて経験したことのない驚くべき日々がきっと」、そう言ってウィンクを一つ。 |
||||
|
思わず顔が真っ赤になった。腰の後ろに羽が生えている。舞台裏での場面を想像、無茶苦茶興奮した。嫌らしい想像は後で後悔したけれど正直な気持ちではあった。これはベタ惚れだな、最初から分かっていた。 |
||||
|
説得されてしまった僕。気分はすでにスター誕生、目を閉じたまま契約書にサインする。天にも昇る心地だった。ついに幸運がやってきた。名案のクロブキー王国を考えだした自分を誉めてやる。ポーランの力を借りてセレブの世界へ突入。ウォーホル君をやっつけて喜んでいたのともお別れだ。ささやかな20分の名声もバイバイ!僕の未来が始まろうとしてる。思わず歌にしたくなった。 |
||||
|
ポーランは宮廷の控えの間に住み始めた。契約を取ろうと電話をかけて数日が過ぎていく。僕はと言えば甘い夢に身を浸していた。数週間のストレスを洗い流していく。「絶対会わせてね」、しつこくポーランに頼んでおいた。バランスを考えてみれば当然ではあった。僕のような王様が一般人、普通の取り巻きに甘んじているはずはなかった。「鳥女の名声がね…」、ミントキャンディーの合間にポーランが言っていた。「…あなたの運命を決める切り札になるのですよ」 |
||||
|
「スターはスターの世界で。鳥女はあなたの枝に」 |
||||
|
まさにその通り。否定のしようもなかった。 |
||||
|
ポーランにじらされているのは分かっていた(何度も質問するので僕が待ち遠しくしているのは分かっているはずだった)。それでも堪えきれず妄想に。毎晩毎晩夢に現れてくる。僕たち二人は巨大な金の鳥籠にいた。女はブランコに座り、腕を広げ、歌いながら僕を呼んでいた。歩み寄っていく僕。恋心で熱に浮かされた僕。ポーランが現れる。いかにも切れそうな巨大モンゴウイカを振り上げていた。 |
||||
|
「仕事の時間だぁ!」 |
||||
|
汗びっしょりで目が覚めた。枕が潰れている。両手には羽毛を掴んでいた。 |
||||
|
有能な座長のお陰かどうかは知らないが全てはあっという間に過ぎていった。独占記事だと信じきった批評家連中相手に幾つもインタビュー。突飛な質問にもひとつひとつ丁寧に答えていった。「世界の重要な戦略拠点についてご意見お聞かせ願いますか」。「女優の…が結婚しましたね」。「バドミントンの世界選手権決勝についてどう思われますか」。何でこんな面倒な質問をしてくるのか分からなかった。俳優でもスポーツ選手でもロックスターでもないのに。しょうがない。これが慣例という奴だった。メディアの台風が巻き上がっていく。 |
||||
|
ポーランは声明を出していた。「ラディスラス1世が観光でフランスを訪問されます」。町の雑貨屋が出資してくれた黒のリムジン(車体脇に宣伝がしてあった)に乗って王国を出発。崇高な一瞬だった。群集はガラスに顔を押しつけてくる。一番熱心な連中は唇でナメクジの跡を残してくれた。僕は有頂天だった。ポーランは手帳を覗きこんで計算をつづけている(「計算能力。人間が動物と違うのはこれだね」)。僕はポーランを信頼しきっていた。しかもこのフランスの首都ツアーが終了したら鳥女に会わせてもらえる、そんな約束になっていた。 |
||||
|
報道陣の期待には応えるつもりだった。女性用品専門店、僕はクロブキー王国の特製料理を披露する。ジャガイモ・オムレツ、唯一まともに出来る料理だった(「本物に戻れば良いんですよ」、思いつきで言った言葉にメディアは飛びついていた)。有刺鉄線を張るのにどうすればいいか、写真で実演したのが日曜大工の月刊専門誌に掲載される。王家大好きな雑誌のために正式な肖像写真も何枚か撮ってもらった(「彼の心を捉えるのは?」、そんなタイトルがついていた。鳥女が見たらどうするんだ)。TVでも大忙し。ヴァラエティ番組に出演、人気作曲家に手直ししてもらったクロブキー国歌を斉唱する。文学議論番組ではアンディ君の影響を語った。午後1時からは報道番組「世界のテロリズムと土着文化最先端」に登場。ポーランが奔走していた。契約の内容まで聞きはしなかったが金回りが良くなって太り始めているのは一目瞭然だった。指輪を嵌めた真ん丸の指が黒ずみはじめていた。小柄で綺麗な宝石だったけれど指輪の部分が細くなり始めていた。 |
||||
|
インタビューでは当たり障りのない話もするように心がけていた。それなのに皆真剣な表情で聞いていくる。考えもしなかった深い意味を読み取っていた。結局は足元をすくわれて僕も手当たり次第の発言を重ねていく。ポーランが言っているように「メディアに操られている傀儡」なのかどうか自分でも分からなくなっていた。どうでも良かった。人々の熱狂は僕の予想をはるかに上回っていた。王党派議員の一人が僕と挨拶している写真を撮られると雑誌での好感度が5ポイントアップ。「本を書いてください」、「CDを出しましょう」、「映画に出演を」、「DVDを」、「似顔絵入りのマスタード瓶を作りましょう」…企画が殺到。熱心な取り巻き連中が僕の世話をしてくれた。手帳を片手にしたポーランは小まめなチェックを怠らず、チケット制度で周りの人間を整理していった。「今どれくらい?」、そう質問するとポーランは声を潜めて「凄いです。凄いですよ」、毎回同じ答えを返してきた。 |
||||
|
クロブキー王国は遥か彼方。時々望郷の念に襲われる。自分の国を密かに「雛の土地」と呼んでいたのだれど(サイズ的には雛ではなくダチョウだった)、早く帰りたくてしょうがなかった。帰国したら前と同じ目であの庭を見る事ができるだろうか。無理ではないか、そんな気がしていた。 |
||||
|
社交界、カクテルパーティー、歓迎会…目が回りそうだった。疲れが溜まって飲みすぎも重なっていた。内臓をやられてしまいトラブル発生。ミントキャンディーの過食とサーモンバターを塗ったトーストの食べすぎ、どこに行くにもまずトイレを探す羽目になる。おまけにケープとレオタード姿、腹具合は思うようにならない訳で、この正装でトイレはちと厳しかった。我慢しようとしたけれども危ない瞬間が何度かあった。ケープが便器で汚れてしまったりとか。幸運なことに礼儀正しく外交儀礼を弁えた人たちと付き合っていたお陰でとやかくは言われなかった。例外はスキャンダル誌。「老化」、「自制もできない」、あれこれ文句をつけてきた。下っ腹の調子不良を堪えるために相当の力を入れていた。集中しすぎて王冠の模様が額に刻まれてしまう。僕が一つ学んだのは「恥ずかしさ」。そう、どんなに偉い人物だって結局は一人の人間にすぎなかった。 |
||||
|
パリ生活がこれで完了。昔読んだ「美・豪・富」誌で僕の王国が取り上げられていた。あれから数世紀が経っている気分だった。クラブ・ダイヤモンズでヴェラと踊っている姿を激写される。続きがどうなったか幾らでも話すことは出来る。綺麗な人だったけれど、いつもあのクラブにいるので家具の一部って気がした。 |
||||
|
8月が終わろうとしている。落ち着きが戻ってくる。そろそろ国に戻ろうかと考えていた。そんな矢先、某有名デザイナー(広告業界でキルトを腰に巻いてレンジャー靴をあわせるのを流行らせた張本人)が新作水着を発表、僕の正装にインスパイアされたケープ付きだった。海辺の町では僕の正装をシンプルにした水着姿の若者連中が浜辺に群れていた。ブランド名「クロブカ」水着の宣伝に借り出される。契約を取ったポーランは満足気な表情だった。 |
||||
|
そろそろご褒美でいいと思ったのだろう。鳥女を紹介してくれた。 |
||||
|
初めて会った時、女の視線は僕から離れようとしなかった。僕は羽の中に優しく飛びこんでいく。 |
||||
|
ここから鳥女がブラジルに出発するまでが僕の人生で一番美しい時間だった。 |
||||
|
|
||||
| 【1】 - 【2】 -【3】 - 【4】 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
] Noirs [ - フランスのもう一つの文学 by Luj, 2008 - 2010 |
||||
|
|
||||